ハムスター・リスについて
 |
病院に行く前に
可能であればケージに入れたままご来院下さい。
床材もいつものままで。糞もそのままで。
無理であれば、移動用の小さな容器に入れて来て下さい。
寒い時期は保温しながらストレスをかけないようにして来院しましょう。
ケージのタイプやまわし車、食器、トイレ、床材など生活環境は、診療に重要なヒントとなります。
病歴がわかる資料や、投与している薬があればご持参ください。
飼い方での注意点
●ハムスターとリスの住居と食生活
1.ゲージの選び方
ゲージには金網タイプと水槽タイプがありますが、どちらもメリット、デメリットがあります。
ハムスターは乾燥状態を好むので通気性のことを考えれば良いです。
しかし、問題点もあります。
金網を噛んで歯を痛めたり、天上に登って落下し体を痛めたり、金網に足が引っかかり骨折したりなど、危険な面もとても多いです。
天井が高いタイプはリスなど木登りをする種類はよいのですが、ハムスターは基本的に高い所に登るのが得意ではないので不適切といえます。
ハムスターにとっては水槽タイプの方が安全かもしれません。
ただし、湿度が上がりやすくなるのでこまめに尿を片づけたり、飲水器から水が漏れてないか、水入れをひっくり返したりしてないかなどの管理が必要です。
※どちらのゲージにしても置く場所も重要です。
直射日光の当たらない、なるべく1日の温度差がない場所が良いでしょう。
また、ハムスターやリスは夜行性なので昼間に人がバタバタするような場所は避けた方が良いでしょう。
ハムスターやリスにも食べていい物と悪い物があります。
主食はペレットフードにしましょう。
体が小さいので余分な物をあげてしまうと少量でもかなり栄養状態が偏ってしまいます。
出来ればおやつは与えない、与えるとしてもほんの少量にするようにしましょう。
ペレット以外に与えてもいい物としては、麦、トウモロコシ、ひまわりの種、にんじん、リンゴなどです。
ただし、こういった物ばかり好み、ペレットを食べない子は注意が必要です。
野菜ばかり食べて痩せてしまったり、ひまわりの種ばかり食べて肥満になったりするのは避けましょう。
・人間のおやつ(チョコレート・クッキーなど)
・牛乳
・ネギ類
・じゃがいもの芽
・チューリップ、スイセンなどの植物
・粘性の高い食べ物や頬袋の中で溶けて綺麗に取れずに腐ってしまいそうなものは避けましょう。
ハムスターやリスは冬眠する動物として知られていますが、飼っているハムスターやリスの冬眠は厳禁です。
ハムスターやリスに冬眠させてしまうとほとんどがそのまま目覚めず死んでしまうからです。
冬眠させない為には、寒い冬も暖かく一定の温度を保ってあげることが大切です。
ヒーターなど使う場合は近くに温度計などを置いて暑くなりすぎたり、寒くなったりしないように気を配りましょう。
よくある病気の例と見つけるコツ
1.不正咬合
食べにくそうかも?!と思ったら、動物病院で定期的に歯を切ってもらいましょう!
ハムスターやリスなどをげっ歯類は、人・犬と違い、歯が生涯伸び続けます。
自然では堅い食べ物を歯を削りながら食べることによって、伸びすぎるのを防げます。
しかし、ペットとして飼われていて、バランスの悪い食事や、柔らかい物ばかり与えたりすると歯が伸びすぎて噛み合わせが悪くなります。
また、金網のゲージなど硬すぎるものを必要以上にかじることによって歯が曲がって噛み合わせが悪くなったり、食事が偏りカルシウム不足により歯が弱くなってしまうことも原因になります。
不正咬合になった場合、放っておくと口内や皮膚をつき破ってでも伸び続け、食欲が落ちてきます。
目やにが出ていたり、左右の目が対称でないことに気付いたら、動物病院で診察してもらいましょう!
ハムスターやリスなどには多く起こる病気の一つです。
目の大きさはわずか数mmですから、人にとってはちょっとしたことでも、小動物にとっては一大事です。
すぐ失明につながりやすいので、早めの対処が大事です。
手についた細菌が目に入り炎症を起こしたり、敷物のチップなどが目を傷つけたり、ケンカをしたりなど原因は様々です。
また、不正咬合のために歯が目を圧迫し、目やにが出たり涙目になったりします。
酷くなると眼球突出といって目が飛び出てくるようなこともあります。
尿が以前と違う色をしている、排尿回数がいつもと違うことに気がついたら、急いで動物病院で検査を受けましょう!
ハムスターやリスは体質的に尿結石ができやすい動物です。
食べるものによっては尿石が出来る確率はかなりたかくなります。
できてしまった場合、薬を飲ませるか、尿道に石が詰まってしまった場合は、外科的な処置が必要となってきます。
しかし、体が小さい為、麻酔にとても弱いのでリスクの高い手術になります。
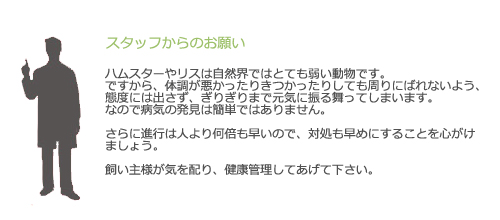
尿検査のススメ
これらの病気は初め、症状がなく気が付けません。
血液検査では見つけられなくても、尿検査では発見できます。
検査は簡単!尿を動物病院に持ってくるだけ!
重症になれば血尿がでたり、尿が出なくなったり、命に関わる事も・・・
検尿によって、発症前に治療できたり、進行を遅らせる事もできます。
尿検査について
◆市販のドライフードを与えている
◆人の食べ物を与えている
◆肥満 等
他にも、結石の元になる結晶ができやすい体質の子もいます。
まだ、症状が出る前にみつければ、
手術や通院をせずに治すこともできるかもしれません。
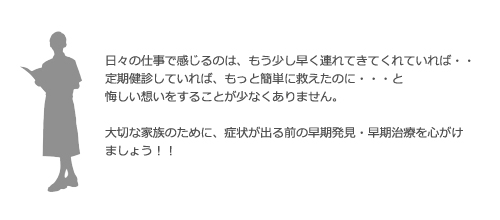
尿の取り方について
①尿をしている時に、綺麗な紙皿をかざして取る。
②トイレがペットシーツの場合、シーツを裏返してそこにした尿を取る。
③トイレが砂の場合、砂を全てはずすか、ラップやビニールなど水分を取られない物を砂の上に敷いて、尿をしたらすぐ取る。
※尿を持ってくる際は、清潔なビニール袋など、水分が吸収されず別の物質が混入しない容器に入れて、1日以内に。無理な場合は冷蔵庫で保管して3日以内にお持ち下さい。
